JAリーダーインタビュー
静岡県JAとぴあ浜松 経営管理委員会会長 渥美保広さん
- 静岡県 JAとぴあ浜松
- 2025年2月

目先の数値よりまずは人を育てよ
一人一人と向き合う。長きにわたって、組合員や職員と、気の遠くなるような対話を積み重ねてきた。
その根底には亡き父の教えがあった。
農家にどなられたあの日を境に
─豊かな水をたたえた浜名湖と、広々とした平野が印象深い土地ですね。
平坦な土地が多く、年間の平均気温は十六度前後あって、とても恵まれた環境だと思います。ぼくも浜名湖のそばで生まれ育ったんですよ。子どもの頃は学校にプールがなかったから、夏はよく湖で泳いでいました。
集落には小規模な農家が二百戸以上集まっていて、戦後の食料増産の時代には「庄内白菜」の産地でした。その後は刺身に添えるパセリや花の栽培が盛んになりました。
うちは兼業農家でしたが、親父の職場が自宅から近かったので、朝晩欠かさず農作業をしていました。
休みの日は家族みんなで畑に行きます。ぼくは二人の弟のめんどうをみながら鬼ごっこをしたりして遊んでいました。体が大きくなると農作業も少し手伝うようになって、野菜を収穫したり、両親が収穫したキクの下葉を取って調製したり……。そんな記憶はかすかにあるんです。でも、一生懸命働いたことよりも、遊んだことのほうがよく覚えているかな(笑)。
ぼくは長男ですから、生涯ここで生きていくのだろうという気持ちがあり、高校卒業後は地元の浜松市庄内農協(当時)に入組しました。
その頃から親父はイチゴの試作を始め、やがて観光イチゴ農園を開きました。働き者で、穏やかな人でしたね。「人にだまされても、だます人間にはなるな」とよく言っていました。人として誠実であれ、ということです。
親父が亡くなったのは、ぼくが四十代半ばのときです。その半年前に余命宣告を受けたのですが、ぼくの息子が「おれがおじいちゃんの後を継ぐ」と手を挙げてくれた。それから彼は農業に専心し、親父が遺した農園を柱に、家業を守り立てています。
─お父様が遺したものは大きいですね。
ぼくは親父の言葉を胸に刻み、誠実に仕事をしようと心に誓いました。その本質をほんとうに実感できたのは、農協で営農指導員をしていた二十代半ばの頃です。
あるとき、先輩職員に同行して農家を訪問しました。栽培技術について話していたのですが、ぼくが意見を言ったらいきなりどなられたのです。当時は仕事にも慣れてきて、営農指導員として言うべきことは言わなければという気負いもあったと思います。だから納得できず、言い返そうとしましたが、先輩にたしなめられました。
そこではっと気づいたのです。農家は栽培のプロです。生活を懸けてやっている。技術はわれわれよりはるかに上なんです。それなのに、ちょっと仕事がわかってきたからといって、「指導」しようなんて……。もっと謙虚な気持ちで人と接しなければいけないと反省しました。
どなった農家も言いすぎたと思っていたようです。これを機にものすごく仲よくなって、胸襟を開いて言いたいことを言い合えるようになりました。「うちに来いよ、飯食ってけ」なんてよく声をかけてもらいましたよ。とてもたいせつな経験でしたね。

─その教訓は、仕事にどう生きましたか。
人に信頼される誠実な仕事をするためには、一人一人と向き合い、相手の視線に合わせて対話をする。そして相手がなにを望んでいるかを理解する。どんなに時代が変わっても、その姿勢と信念を忘れずにいたいのです。
ぼくは四つの支店で支店長を務めましたが、成績が思わしくない支店ばかり任されてね(笑)。職員のやる気を引き出すにはどうしたらいいか、日々考えました。やはり、一人一人をよく観察して対応することですね。十人十色ですから、人によって褒め方や叱り方も変えます。目標を達成できなかった職員には、「この点はがんばっていたよな。ちゃんと見ているぞ」と声をかけたりする。それを続けていくと、徐々に心を開き、相談をしてくれるようになります。遠回りではありますが、目先の数値目標よりも、まずは人を育てること。それが結果として数字に結びつくのではないでしょうか。

「農家に出向く」だけでは足りない
─平成七年に十四JAが合併して誕生したJAとぴあ浜松は、令和七年で三十周年を迎えます。いま、どんなことに力を入れていますか。
一貫して力を入れてきたのは、販売力の強化です。よく「生産振興」と言いますが、売り先が確保できなければ、説得力がありません。六割以上の農産物が京浜市場で販売されていますから、いま東京に職員を駐在させています。市場の仲卸、量販店のバイヤー、加工品業者やその販売会社など、広く接点を持って市況やニーズを把握するようにしています。
ただ、なにをやるにしても、農協の経営がしっかり成り立っていることが大前提です。たとえば「販売高が計画比何パーセント増」などという言われ方をしますが、それは表面的な数字でしかありません。だいじなのは、その数字の中身でしょう。どの分野でどれだけ利益があったか、手数料率はどれくらいか、なぜ手数料率が上がったのか、といった細かい分析が必要ですね。農家の所得を増大させるためには、われわれはなにをすべきか、真剣に考えなければならないのですから。

─ただ、現在は社会の変化が激しく、数か月先も読めない時代です。経営を安定させていくにはなにが必要でしょうか。
常識にとらわれすぎず、発想を変えてみる。いつも同じ方向からではなく、別の角度から物事を見てみるのです。そういった変化を試みなければ、農協だけが時代の波に取り残されてしまうでしょう。
人材育成ひとつとってもそうです。いま、管理職の公募制を取り入れている企業が増えてきています。やりたい人に手を挙げてもらうわけです。こうした取り組みから、わたしたちも学ぶものがあるのではないでしょうか。
営農事業もしかりです。JA職員が農家に出向くことの重要性が盛んに言われてきましたが、もうそれだけでは足りない時代になりました。最新の資材や市場の動向、消費者の嗜好など、農家がいちばん欲しい情報を提供する。職員はそういうことまで把握しておく必要がある。一人が二役三役を担う時代ですね。
さらに、組織のあり方も問われています。既存の職員よりも新入職員のほうがまったく新しい感覚でものが見えていることもあるのです。だからこそ、そうした声を吸い上げられる風通しのよさが求められますね。ぼく自身も、なんでも話ができるような会長でいないといかんな、と思っているんですよ。
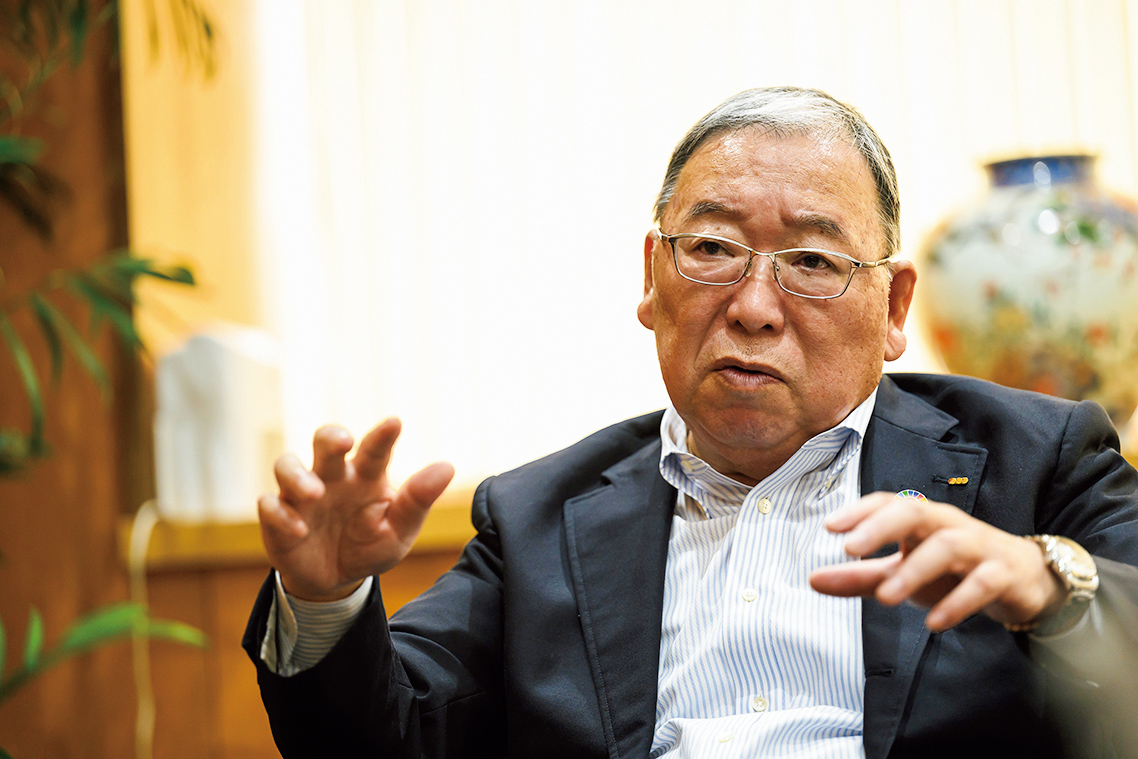
文=成見智子 写真=松尾 純 写真提供=JAとぴあ浜松
 詳細情報
詳細情報
あつみ・やすひろ/昭和三十一年生まれ、浜松市出身。静岡県立引佐高等学校を卒業後、五十年浜松市庄内農協に入組。平成七年JAとぴあ浜松に合併後、人事部長、総合企画部長、営農販売部長などを歴任。二十六年常務理事、令和二年経営管理委員、五年経営管理委員会会長に就任し、現在に至る。
JAとぴあ浜松
平成七年に十四JAが合併して誕生。静岡県の最西部に位置し、平坦な地形と温暖な気候を生かして、葉ネギやタマネギなどの野菜、ミカンなどの果樹、花卉、畜産など多種多様な農畜産物が生産されている。地域に即した営農アドバイザーを配置し、ていねいな営農支援をおこなっている。





